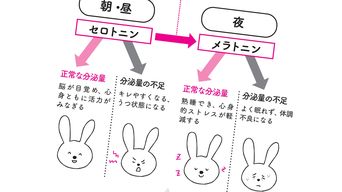イーロン・マスクが9年前に「宣言」したこと
2016年、テスラCEOのイーロン・マスクが世界の自動車業界に衝撃を与える構想を打ち出した。未来の工場を「Alien Dreadnought(エイリアン・ドレッドノート)」(異星の戦艦)と呼び、完全自律化された製造システムの実現を目指すと宣言したのだ。彼の言葉で最も象徴的なのは、「工場は、マシンをつくるマシンである」という一節である。
製品そのものよりも、製品を生み出す工場を進化させる方がはるかに大きな競争力をもたらす。マスクはそう信じ、工場を静的なインフラではなく、アップデートを繰り返す「進化する製品」として再定義した。この逆転の発想は、テスラの製造戦略全体を貫く基盤思想となった。
マスクの思考法の根幹には「第1原理思考(First Principles Thinking)」がある。常識や前例を前提にせず、物理法則のレベルまで掘り下げ、ゼロから組み立て直す。従来の自動車産業が「車を改良する」「人を教育する」という漸進的アプローチに固執していたのに対し、彼は問いを逆転させた。
「そもそも工場自体を製品と見なせばよいのではないか」
この発想により、工場は単なる裏方から競争優位を生み出す最大の“製品”へと格上げされた。
壮大な未来予測が現実になりつつある
成果を定義する数式も独自だ。
量を増やし、密度を高め、速度を極限まで引き上げれば、指数関数的な生産性の向上が可能になる。
実際にテスラはこの思想を基に、ギガプレスによる一体鋳造、生産工程の並列化、デジタルツインによる仮想検証を矢継ぎ早に導入してきた。さらに、工場を「Alien Dreadnought 0.5」「1.0」「3.0」とソフトウェア的にバージョン管理する発想まで持ち込んだ。これまで「改善活動」の延長でしか工場を捉えてこなかった業界にとっては革新的であり、製造現場そのものをイノベーションの舞台に変えていった。
そして、その思想の延長線上にあるのが、人型ロボット「Optimus(オプティマス)」である。工場における人間労働を代替し、生産速度と柔軟性を飛躍的に高める。マスクは今、人型ロボットが無数に稼働する工場という未来像を現実に近づけつつある。