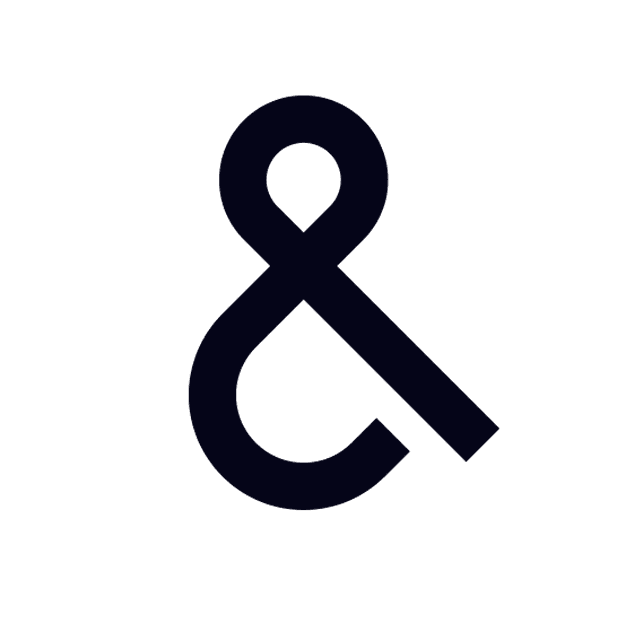〈住人プロフィール〉
47歳(自営業・女性)
戸建て・4LDK・丸ノ内線 南阿佐ケ谷駅・杉並区
入居13年・築年数19年・夫(会社員・48歳)、次男(16歳)との3人暮らし
教師の母は、料理が苦手そうだった。
「おそらく料理に興味がないんです。おまけに忙しい。なのに帰宅したら大急ぎで、私たち三人姉妹と父のために、ご飯を作る。でも、どれもあまりおいしくないんですね。だからさりげなく“これだけでいいよ”と言っても、副菜まで作らなければと思っている。子ども心に、頑張ってるな、大変そうだなと思いながら見てました」
たとえばカレーは薄い。つい分量よりお湯を多めに足してしまうからだ。ジャガイモはジャリジャリ、ニンジンも芯がある。ホウレン草のおひたしは、いつも「びしょびしょしている」。
幼い頃はこういうものだと思っていたが、友達の家でご飯を食べたとき、「あれ?」と気づいた。どうやら母は料理が上手(うま)くないらしい、と。
高3の受験後、時間ができたとき初めて料理本を見ながら、和食を作った。メニューは忘れたが、定番の総菜だったことだけは覚えている。
レシピ通りに作ったら、びっくりするくらいおいしくできた。同居の祖母がおいしいねと何度も褒めてくれる。──ちゃんと作ったら、料理ってこんなにおいしいんだ。
それから、毎日夕食作りをかってでた。「料理が大好きになったのは、あの高3の春です」と、振り返る。
本稿にそのまま書いて、ご実家のお母さんは大丈夫かと尋ねると、笑いながらこう語った。
「布団を干したり、花を生けたり、日本茶を淹(い)れたりするのは好きで、暮らしを自分なりに楽しんでいる人。今は帰省すると、すべて私が作りますが、屈託なく喜んでいますし、自分の料理についてとくに気にしていない。だから大丈夫です!」
女だから、あるいは母親だからといって、誰もが自然に料理が好きになるとは限らない。
性差に限らず、元から興味を持てない人、味に無頓着な人だっている。
それでも親だからという理由で頑張ろうとする母に、心を寄せる親子の関係こそかけがえがない。
偶然か必然か、3姉妹とも大の料理好きに育ち、長女の彼女はフードディレクター、次女は料理家のマネジメント、三女は料理雑誌編集者の職に就いた。
褒めない、食べない家族に「イラッ」
「作るのが好きだけど、人に喜んでもらうのはもっと好き」と語る彼女は、手作りパン歴約20年。分量を暗記しているほど好きなバターシュガーパンとチーズパンは、秋冬は毎週作る。
だが、「夫や次男は私のパンに飽きているので、もっぱら人にさし上げるために焼きます」。
長男は大学進学で家を出たため、現在は次男、夫との3人暮らしである。ふたりともよく食べるが、料理で「マジギレすることもしょっちゅうある」と自嘲する。
「先日も、トッポギに挑戦して、高校生の次男に出したら、全然手をつけないんです。“こんなに一生懸命作ったのになんで食べないの?”と言ったら、“タレ洗ったら食べる”。じゃあ自分で作りなよ!!“と、マジギレしたばかりです」
夫にこぼすと、「高校男子なんてそんなもんさ。トッポギなんて目新しいもの食べやしないよ」。
その夫も、「帰りが遅いので一緒に卓を囲めず、食べても昔は“おいしい”と、なかなか言わなかった。“ねえ、なんか言ってよ”と、しつこく感想を強制して20年、やっとポツポツ言うようになりました。実家の父も、どんなに手間暇かけたものも、1分で食べ終わってしまう人。ほんと、食べたらなんか言って欲しいですよね」。
横で写真家の本城直季さんが、「どの家庭でも、あるあるです」と思わず噴き出していた。
仕事で料理の提案をし、自宅で試作し、さらにプライベートで菓子もパンも新しい料理にも挑戦する。「喜んでもらうこと」が好きな彼女は、家族3人が唯一揃(そろ)う朝、腕によりをかける。
そのため朝からグラタン、パエリア、パスタも普通なのだと言う。
18の春から今も、彼女の心をとらえて離さない料理の魅力とはなんだろう。
「独身時代、料理雑誌や新聞の料理記事を切り抜いてスクラップしていたノートを、今も見返しては書き足したり、自分の家族用に分量を上書きしたりしています。いまだに、新しいレシピを見ると“これはどんな味がするんだろう”と、想像してわくわくする。レシピ通りに作ると、必ずおいしいですし、だんだん腕が上がる。無限に新しい味にチャレンジできるのも楽しいです」
仕事の現場では最近、市販の合わせ調味料を使ってパパッとできるものを求められることが多い。「便利だけれど、いつも同じ味で飽きてしまうのが寂しいです」と顔を曇らせる。
「ドレッシングでも炒め物のたれでも、自分で一から作ると、同じ材料でも微妙にその日ごとに味が違う。気持ちや天気や季節でも変わる。パン作りが好きなのも、出来上がりが毎日違うからです」
一流シェフたちの手間暇かかった料理に仕事で立ち会うと、ああこうするとおいしくなるのかと、必ず学ぶところがあるという。たとえば肉や魚や野菜の下処理、オイルの使いかた、素材の旨(うま)みの引き出しかたなどなど。
しかし最近は、そのような料理の仕事の需要が減っている。
シミと書き込みだらけのスクラップブック作りが好きなのは、「ウェブのように流れていかないから」。
ウェブの利便性を十分理解し、仕事でも全力を注ぐが、自分は25年以上続けている、のりとハサミと手を使って切り貼りしたものの方が、脳に深く記憶されるようで相性がいい。
取材の途中、制服姿の次男が帰宅した。
はにかみながら首を小さくコクンと振って我々に挨拶(あいさつ)した彼は、「パンあるよ」と言う母の声に、食卓の端に座る。そして無言で、カラメル色に香ばしく焼けたバターシュガーパンに手を伸ばした。
特段リアクションはない。
「くだものが大好きだそうで、スナックやお菓子が嫌いって珍しいですね」と私が声をかけると、さらりとなんでもないふうに教えてくれた。
「友達と野球部の帰りにコンビニ寄るんですけど、俺は食べないです。どうせすぐ家で夕ご飯になるし、ごはんのほうがうまいんで」
じつは、応募メール文にも、取材が始まった直後も、しきりに彼女は気にしていた。「私の台所は、『東京の台所』に出てくるみなさんのようなドラマも、出会いも別れも喪失も何もないんですが、大丈夫でしょうか」
もちろんです、と答えた。
友達と部活帰りにコンビニに寄ってもひとり何も買わない野球少年。家族がさりげなく阻止するのに、頑張って苦手な料理をふた皿も三皿もこしらえようとする母を想像するだけで、胸の奥がほんのりあたたかくなる。それで十分だ。
3月26日開催のオンライントークイベントへのたくさんのご参加ありがとうございました。その際、多くの方から「東京以外の台所も見たい」という声をいただき、番外編を実施します! 今回は「神奈川の台所」です。5月11日までに「東京の台所2」応募フォームへご応募お待ちしています。