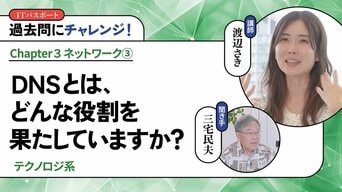出社勤務とテレワーク、どちらが良い働き方なのか。麗澤大学工学部教授の宗健さんは「イノベーティブな仕事ほど実はテレワークに向いていない。週5日でなくてもいいが、同じ場を共有することが重要だ」という――。
テレワーク実施率は、わずか13.3%
新型コロナ禍で一気に普及したテレワークだが、その実施率は思ったより低い。
筆者が企画、設計、分析に関わっている「いい部屋ネット 街の住みここちランキング(以下「住みここちランキング」という)」の設問には、働き方に関する設問がありテレワーク実施率を算出できる。
図表1は、2021年以降のテレワーク実施率を集計したもので(2020年・2019年は設問が無かった)、テレワーク実施率は2021年には18.9%だったが、2025年には13.3%に低下している。
類型でみても2025年の結果では、「ほぼテレワーク」は3.8%に過ぎず、テレワーク主体(出勤あり)が3.4%、出勤主体(テレワーク有り)が6.1%となっている。
テレワークという働き方は、メディアでの報道などから受ける印象よりもずっと少ない。
テレワーク実施率が高いのは首都圏
テレワークの実施率は、地域や職種、業種でも大きな差がある。
住みここちランキングの個票データをさらに集計してみたものが図表2から図表6である。
地域別に見ると、首都圏(一都三県)のテレワーク実施率が23.4%と高いが、近畿圏(二府三県)では13.0%と全国平均並みになり、その他地域は8.1%と低くなっている。
職種別に見ると、会社経営者・役員が24.8%、会社員(管理職)が24.0%、正社員(技術・研究職)が20.7%、自営業・自由業が21.3%、派遣社員(技術・研究職)が21.9%、契約社員(技術・研究職)が23.6%、正社員(事務職)が18.8%、派遣社員(事務職)が19.8%、契約社員(事務職)が19.8%などとなっている。
一方、公務員は6%程度、製造・現場職は2%程度、パートは3.8%、アルバイトは6.7%などと低くなっている。