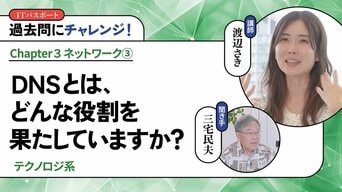「朝はなかなかエンジンがかからない」
こんにちは、産業医の武神です。毎年秋口から年末にかけて、産業医面談では「なんとなく気分が重い」「午前中とくに仕事のギアが入らない」「ふと寂しい感じがする」といった不調の相談が明らかに増えます。夏の疲れが残っている側面もありますが、この時期の不調の大きな背景には、日照時間の減少という季節的要因が深く関わっています。
そこで今回は、この仕組みと対策となる習慣についてお話しさせていただきます。
私のクライエントの衛生委員会で毎月顔を合わせるAさん(50代)は、ベテランで同僚からの信頼も厚い人です。彼女は毎年、夏が終わり涼しくなり始めると、決まってこう口にします。「ああ、またこの季節がやってくる」。
この時期Aさんが感じ始める不調は、深刻な抑うつとは少し異なります。具体的には、朝、布団から出るのに時間がかかるようになり、「朝はなかなかエンジンがかからない」と感じます。午前中は、集中力が散漫になりがちで、周囲からは「秋口は少し静かで、テンポが遅くなる」と認識されているようです。
日照時間の減少に伴う体内リズムと気分の変化
しかし、食欲は普通にあり、眠れないわけでもありません。ジム通いも今まで通り継続しています。Aさん自身が職場でこれまで見てきたメンタル不調者や休職者に比べると「そこまで調子が悪いとは感じない」と、自身の状態をAさんは客観的に捉えています。本人の言葉を借りると、「職場の人間関係も仕事内容も、プライベートでも、特別なストレスは感じないけれど、とにかく秋は気分が不調」という状態です。薬に頼ることは避けたいものの、何らかの手は打ちたいと、毎年、新たにできることがないかの相談に産業医面談に来てくれます。
私は、Aさんの訴えと毎年繰り返されるパターンから、これには季節性の気分変動の影響が強く関わっていると感じました。具体的には、日照時間の減少に伴う体内リズムの変化と、それに伴う気分の変化です。
そこで、Aさんには薬物療法ではなく、以下の具体的な生活習慣の改善策を提案し、実践してもらっています。
まずは、朝一番の日光浴。朝起きたらすぐに、日光を意識的に浴びること。具体的には、時間的余裕があれば自宅で窓の近くで15分ほど過ごす。難しい場合は、通勤途中に一駅歩くなどして、意識的に屋外で日光を浴びることです。
昼休みは、ビルの地下街などを歩くのではなく、地上を歩いて日光を浴びるようお願いしています。天気が良ければ近くの公園でお昼を食べることも伝えています。これは気分転換にもなり実践しやすいようです。