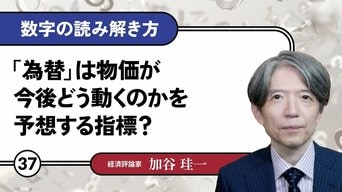家計を共有する場合、一括管理が大原則
ウェブデザイナーの山下幸子さん(仮名・52歳)は2年前から私どもの事務所に通っています。相談内容は主に2つ。1つは再婚相手との家計の共有方法。2つ目は老後に向けてどう資産を運用すべきか、です。
幸子さんは子なしのバツイチ。大学を卒業後、ずっとフリーのウェブデザイナーとして働き、ここ数年は手取りで月48万円程度の収入を維持しています。比較的高収入ですが定期預金や株式投資などで堅実に資産を築き、30代でマンションも購入。預貯金と投資口座を合わせた資産は、相談時点で4500万円。
そんな幸子さんが50歳を過ぎて、同い年のパートナー(IT系企業の会社員)と再婚することに。
「バツイチ同士の再婚ですし、今回の結婚ではもめる要素を最小限にし、パートナーと穏やかに余生を送りたい。そのために、どう家計を共有していけばよいのでしょうか。
また、老後にもらえる国民年金は6万円台が想定されるので、わずかな年金額を補うために今後はどんな資産運用をしたらよいのか教えてください」
と、ご相談に来られたわけです。
早速、1つ目の課題から着手。ファーストステップとして、現状を把握するために、家計簿をつけて支出を「見える化」していただくことに。自営業である幸子さんの手取り月収は48万円で、ボーナスなし。現状、入籍前に先行して二人暮らししており、その支出は54万2000円です。
この約54万円を、どう分担すればよいのでしょうか?
夫婦で財布を別にしながら、「住宅費などの固定費は夫、食費などの変動費は妻」というように品目ごとに支払い担当を振り分ける方法もありますが、私共はおすすめしていません。家計簿などで共有できていたらよいのですが、互いの懐具合と家計の全体像が見えにくくなり、「ふたを開けてみたら貯蓄が全然できていなかった」といったケースをたくさん見てきたからです。
それよりは、家計管理が得意な方が財布を握り、もう片方から一定の生活費を入れてもらい、その中でやりくりする「一括管理」のほうが全体が見えて貯めやすいです。幸子さんは、家計管理が得意で貯蓄の実績もあるので、ご自身が管理することになりました。
ただ、住宅費15万円は、もともと幸子さんが所有していたマンションにパートナーが引っ越す形になったので、従来通り幸子さんが住宅ローンなどを支払うことに。また、すでに入っていた生命保険や個人のスマホ代も、引き続き各自の財布から出し、それ以外の生活費はパートナーから25万円をもらってやりくりする形で決まりました。
幸子さんの手取り48万円+パートナーからの生活費25万円から54万2000円の支出を差し引くと、月18万8000円が残る家計になります。この収支の是非は、後述します。