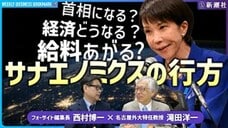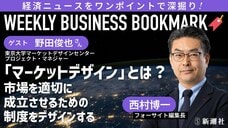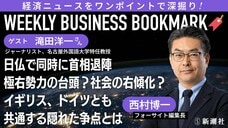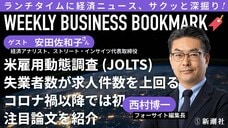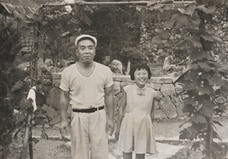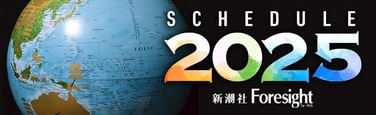第27回参議院選挙が終わった。参政党と国民民主党が躍進し、与党は過半数を割り込む結果となった。
今回の選挙で、私が注目するのは、松田学氏の当選である。2012年に日本維新の会から立候補して衆議院議員に初当選して以来、今回が二度目の当選で国政復帰となる。
松田氏は2020年4月の参政党結党に関与し、2021年12月からは共同代表、2022年7月から2023年8月までは代表を務めるなど、党内で中心的な役割を担ってきた、いわば「参政党の重鎮」である。
私と松田氏とのご縁は、かれこれ20年来に及ぶ。きっかけは、昨年4月に逝去されたマッキンゼー元東京支社長・横山禎徳氏からのご紹介であった。当時、私たちの研究室は東京大学医科学研究所にあり、月に一度、横山先生をお招きして勉強会を開催していた。その場に、松田氏も毎回のように参加していたのである。松田氏は、自らを「横山先生の弟子」と称するのが口癖であり、その学びへの真摯な姿勢が印象に残っている。
2006年、私は当時参議院議員であった鈴木寛氏(現・東京大学公共政策大学院教授)らとともに、「現場からの医療改革推進協議会」を立ち上げた。その際、横山氏と松田氏には、発起人として名を連ねていただいた。
私は松田氏の人柄と見識を尊敬している。松田氏も、私を評価してくれていたようだ。新型コロナ流行後は、松田氏が主宰するYouTubeチャンネルにお呼びいただき、議論したこともある。
松田氏は、県立千葉高校を経て東京大学経済学部を卒業し、大蔵省に入省した元エリート官僚である。私や横山氏とも気が合い、率直な議論ができる間柄だったことからも、当時の松田氏は、現在一般に参政党に抱かれているような「過激な保守派」の印象とは無縁であった。それだけに、近年の彼の言動の変化には、正直なところ少なからぬ驚きを抱いている。
私が注目するのは、彼が京都生まれであることだ。そもそも松田という名字は西日本に多い。元は関西の一族なのだろう。このあたり、名字の分布を知りたい人には「名字由来net」をお勧めしたい。
私が出身地にこだわるのは、人格の多くが、幼少期から高校生くらいまでに形成されると考えるからだ。その過程で最も大きな影響を与えるのは、家族と友人である。家族の価値観は、地域の歴史や文化的背景に強く影響される。東京人と大阪人に異なる印象を抱くのは、その象徴的な一例だ。友人の多くは学校で出会うものであり、公立・私立を問わず、学校は創設者や地域社会の理念を反映している。このように、生まれ育った土地の地域性は、各人の人格に少なからず刻み込まれている。
関西、なかでも畿内は、日本の中でも特異な歴史的背景を持つ地域である。畿内とは、京都・大阪・奈良に加え、兵庫県の阪神間を含むエリアを指す。この地域には、江戸時代を通じて大藩が置かれなかった。徳川家康が、外様大名と京都の皇統の権威、大坂の経済力が結びつくことを警戒したためとされる。
一方、畿内の周辺には親藩や譜代の有力大名が配置された。たとえば、彦根の井伊家、紀州徳川家、姫路の酒井家(雅楽頭家。庄内藩左衛門尉家と並ぶ酒井宗家)などが挙げられる。
私は畿内に大藩が置かれなかったことが、この地域の教育を「独自」のものとし、ひいては関西人特有の気質を育んだと考えている。
地域のエリート層に息づく「藩校」の価値観
この点について論じる前に、まず我が国の教育制度の歴史的背景を概観したい。我が国の近代教育制度は、明治期から戦前にかけて整備されたものであり、その基盤には旧藩校の伝統が色濃く残っている。
たとえば、東京大学の前身は、江戸幕府によって設立された蕃書調所および医学所を源流とする東京開成学校と東京医学校である。とくに東京医学校には、佐倉藩の順天堂から佐藤尚中らが招聘され、幕末から明治初期にかけての医学教育の継承に重要な役割を果たした。同様に、東北大学は、仙台藩の藩校・明倫養賢堂を、九州大学は、福岡藩の藩校・賛生館をそれぞれ前身としている。
高等教育を受けた人材が極めて限られていた明治期において、幕藩体制下の教育資源を活用するのは、合理的な選択であった。
このことは、高校教育にも影響を及ぼしている。たとえば、福岡県立修猷館高校、岡山県立岡山朝日高校、福井県立藤島高校、滋賀県立彦根東高校、神奈川県立小田原高校など、旧藩校の流れを汲む名門校が各地に存在する(参照)。私立学校として運営されている広島県の修道高校を除き、これらは公立の進学校として高い水準を維持し、現在に至るまで地域のリーダーを輩出してきた。
それぞれの校風も、旧武士階級の精神性を色濃く反映している。たとえば「質朴剛健(修猷館高校)」、「赤鬼魂(彦根東高校)」、「至誠無息(小田原高校)」といった校訓は、その象徴である。
こうした学校の多くは、制度上は明治期の廃藩置県によって藩校とは断絶しているものの、現在に至るまで武士道的価値観を受け継いでいる。これらの精神は、地域のエリート層に求められる素養として、現代にも脈々と息づいているのだろう。
畿内伝統校の価値観は「武士道」よりも「ディール」?
話を畿内に戻そう。この地域の大きな特徴は、旧藩校の伝統を受け継ぐ高校がほとんど存在しない点にある。例外として挙げられるのは、兵庫県三田市の三田学園であり、同校は九鬼家が治めた三田藩の藩校の流れを汲んでいる。
しかし、そもそも畿内には江戸時代を通じて大藩が置かれなかったため、藩校そのものがほとんど存在せず、その伝統が近代教育に引き継がれることもなかったのである。
この地域の教育における特徴の一つは、宗教団体や造り酒屋が設立した学校が多いことである。たとえば、大阪の北野高校は、明治6年に大阪府が難波東本願寺掛所に設置した欧学校を起源とする。大阪星光学院はカトリック教会系のサレジオ修道会が、兵庫県の灘高校は菊正宗・白鶴・桜正宗といった灘五郷の造り酒屋が、京都の洛南高校は真言宗が、奈良の東大寺学園は東大寺がそれぞれ母体となって創設された。
校訓にもその背景が色濃く表れている。大阪星光学院は新約聖書『マタイによる福音書』に由来する「世の光であれ」、洛南高校は仏教の三帰依(自己を尊重せよ、真理を探究せよ、社会に貢献せよ)を掲げる。灘高校の校訓は、「精力善用・自他共栄」という、柔道の理念に基づいた実践的倫理観である。
これらは、前述の旧藩校に由来する「質朴剛健」や「至誠無息」といった武士道的な規範とは対照的であり、畿内における教育の独自性を象徴している。
私は、旧藩校の教育は政治家の育成に、畿内の高校教育は実業家や学者の育成に適していると考えている。前者が重視するのは「権威」による資源の配分であり、後者は「取引(ディール)」を通じた調整と交渉に基づくものである。
権威を成り立たせるには、正当性や信頼といった要素が不可欠である。その意味で、「質朴剛健」「赤鬼魂」「至誠無息」といった旧藩校に由来する校訓は、日本人が政治的リーダーに求める資質を体現しているといえるだろう。
一方、「真理を探究せよ」や「自他共栄」といった理念は、学者や実業家にふさわしい精神性を示している。論理的思考、独立性、そして相互利益を重視する価値観である。
こうした教育的背景を踏まえれば、明治維新において京都の公家や大阪の商人が大きな役割を果たしたにもかかわらず、畿内出身の総理大臣が西園寺公望、幣原喜重郎、鈴木貫太郎、東久邇宮稔彦、芦田均の5人に限られていることにも、一定の合理性を見出すことができる。
一方で、ビジネス界に限らず、自然科学の分野でも関西の高校が卓越した人材を輩出していることは注目に値する。たとえば、灘高校出身の野依良治氏、大阪教育大学附属高校天王寺校舎出身の山中伸弥氏を含め、関西圏の高校出身者からはこれまでに8人のノーベル賞受賞者が出ている。
これに対して、首都圏の高校の卒業生では、湘南高校出身の根岸英一氏、日比谷高校出身の利根川進氏など4人にとどまる。首都圏の人口が関西の約2倍であることを踏まえれば、この数字の差がいかに大きいか、お分かりいただけるだろう。
近年、日本の政治において関西出身の政治家が顕著な影響力を持つようになっている。たとえば、東京都の小池百合子知事、神奈川県の黒岩祐治知事、千葉県の熊谷俊人知事はいずれも関西出身である。小池氏は甲南女子高校、黒岩氏は灘高校、熊谷氏は白陵高校の出身であり、甲南と灘は実業家、白陵は塾経営者によって創設された学校である。
国政でも関西出身者の存在感は大きい。旧安倍派のいわゆる「5人衆」の中で、西村康稔氏(灘高校卒)と世耕弘成氏(大阪教育大学附属天王寺高校卒)はいずれも関西出身である。
次期総理候補の一人とされる高市早苗氏も奈良県出身で、奈良県立畝傍高校を卒業している。
また、日本維新の会は大阪発の地域政党として誕生した。創設者の橋下徹氏は大阪の北野高校出身、現在代表を務める吉村洋文・大阪府知事は大阪府立生野高校、共同代表の前原誠司氏は京都教育大学附属高校の卒業生である。
さらに、れいわ新選組の山本太郎氏は兵庫県宝塚市出身で、箕面自由学園を中退。NHKから国民を守る党の立花孝志氏は大阪府泉大津市出身で、大阪府立信太高校を卒業している。2023年に日本保守党を立ち上げ、2025年の参議院選挙で当選した百田尚樹氏も大阪市生まれで、奈良県立添上高校の出身である。
今回の選挙で躍進した参政党の神谷宗幣氏も、生まれは福井県高浜町だが、関西大学への進学以降、大阪を政治活動の拠点としている。
こうして見てくると、多党分立が進む現在の政界において、関西出身の政治家が主導的な地位を占めていることは明らかである。そして、彼らの政治スタイルは、従来型の日本の政治家とは随分と異なる。私は、この状況に危機感を抱いている。
情念の長州人と「抑制の装置」としての宏池会
戦後の日本政治は、実のところ一貫して「西国」出身の政治家によって主導されてきた。平成以降、19人の総理大臣が誕生したが、そのうち現在の石破茂総理を含め、実に8人が九州・中国・四国地方の選挙区から選出された政治家である。さらに、鳩山由紀夫氏や菅直人氏も、政治的な出自は東国にあっても、一族は西国にルーツを持つ。
これらの地域の総人口はおよそ2500万人。日本全体の人口の約2割に過ぎないにもかかわらず、平成以降も総理大臣の約半数をこの地域が輩出しているという事実は、極めて異例である。背景には、徳川幕府を打倒した「西国雄藩」が持つ歴史的正統性と、その影響力の残滓があるのだろう。
とりわけ明治維新を牽引したのは、薩摩藩と長州藩であり、特に後者の影響は際立っていた。その中心にいたのが、吉田松陰の松下村塾で学んだ若者たちである。「諸君、狂いたまえ」という言葉に象徴されるように、彼らは国家の理想に殉じ、非業の死を遂げた者も少なくない。
では、何が彼らをそこまで突き動かしたのか。ある長州藩志士の末裔は、「それは抑圧された下級武士階層に宿るルサンチマンであった」と語る。吉田松陰を今なお神格化する山口県では、ルサンチマンを原動力とし、国家のために過激に行動する人物を評価する風土が根強く残っている。
こうした歴史的背景を踏まえると、山口県出身の歴代首相の言動も、異なる視点から読み解くことができる。たとえば岸信介である。彼は山口県田布施村(現・田布施町)の出身で、父・秀助は下級武士だった佐藤家に婿入りし、信介は父方の実家にあたる岸家の姓を継いだ。
若き日の岸は放蕩気味だったとされるが、東京帝国大学在学中に頭角を現し、卒業後は農商務省に入省。その後、同郷で後の外相・松岡洋右や、長州出身の実業家・鮎川義介らとともに満州国の建国構想を推進し、中枢に関わった。戦後はA級戦犯容疑で収監されるが、政治的復権を果たし、首相として日米安全保障条約の改定に全力を注ぐ。この条約改定は、全国的な反対運動を招いたが、岸は政治生命を懸けて断行した。その激しさと信念の強さは、典型的な「長州人」の気質を体現していると言えるだろう。
郷土の偉人を理想像として敬愛するのは、官僚も例外ではない。たとえば財務省元事務次官・矢野康治氏も、その一人である。下関西高校から一橋大学を経て、1985年に大蔵省に入省。東大卒が大多数を占める同期25人の中で、非東大卒ながら主税局を中心に着実に歩を進め、最終的に同期で唯一、財務省事務次官にまで上り詰めた。
在任中の2021年には、月刊『文藝春秋』に寄稿し、与党などの財政政策を公然と批判して波紋を呼んだ。その際、彼はその行動の動機を「やむにやまれぬ大和魂」と表現し、吉田松陰の言葉を引用して自らの姿勢を説明した。ここにもまた、長州的精神性の現代的な継承を見ることができる。
長州出身者を中心とする政治勢力に対抗してきたのが、宏池会を軸とするリベラル保守の流れである。宏池会の歴代会長の選挙地盤を見ても、池田勇人・宮澤喜一・岸田文雄の広島、大平正芳の香川、古賀誠の福岡と、いずれも長州を地理的に取り囲む地域に位置しており、象徴的である。
宏池会系の政治家は、長州出身者に比べて権力闘争には不向きとされることもあるが、その一方で、財務省をはじめとした中央官庁、知識人層、さらには朝日新聞に代表されるメディアなどからの支持を集めてきた。
こうした勢力は、イデオロギーや情念を前面に押し出す長州的な政治スタイルに対して、現実主義や抑制の美徳を重視する点で対照的である。その結果として、長州的過激主義が暴走することを防ぐ「抑制の装置」としての役割を、戦後日本の政治において果たしてきたと言えるだろう。
政治の多様性確保と均衡に欠かせない「地方の力」
安倍政権の特異性は、「長州」と関西出身の政治勢力が連携した点にある。たとえば、安倍派の「5人衆」に名を連ねた西村康稔氏や世耕弘成氏はいずれも関西出身であり、日本維新の会や、冒頭で触れた参政党の松田氏らも安倍政権を支持した。
さらに、百田尚樹氏、西村眞悟元衆議院議員、青山繁晴参議院議員といった保守系の論客も、いずれも関西を拠点とする人物であり、その多くが安倍政権に強い支持を表明してきた。
彼らの政治理念そのものについて、私には明確に理解できない部分もある。しかし、安倍晋三元総理の主張を支持することで、自らのメディア露出を高め、政治的・社会的影響力を拡大するという点においては、きわめて合理的な振る舞いだったのではないかと考えている。そうした行動の背後には、関西出身のリーダーにしばしば見られる「ディール志向」、すなわち取引的・実利的な価値判断があるように思えてならない。
一般論として、高齢化が進行すれば、国家は次第に経済的な活力を失い、同時に社会の格差も拡大する。そのような状況では、保守・リベラルを問わず、社会の不満を代弁する形で過激な言動が支持を集めやすくなる。SNSの発展によって、こうした言説が瞬時に拡散される現代では、なおさらその傾向が強まっている。
このような暴論に対抗できるのは、冷静な理性である。かつて日本の政治と官僚機構を支えてきたのは、穏健で中道的な政治勢力だった。政治のリーダーたちは、しばしば山口県を取り囲む西国の地方都市から輩出され、江戸時代以来のエリート教育の伝統を受け継いできた。
現在の石破総理、林芳正官房長官、森山裕幹事長による政権体制も、まさにその系譜に連なる。石破氏がクリスチャンであり、リベラルな政治思想の持ち主であることは、あらためて説明を要しないだろう。
森山氏は、鹿児島県の大隅半島出身で、夜間高校を卒業し、地方議会から国政へと歩んだ叩き上げの政治家である。その穏健で地に足のついた政治姿勢は、地方出身の中道保守の伝統を体現している。
林氏は、解散前の宏池会に所属し、長州的な過激主義とは明確に距離を置く政治家である。知人である長州藩出身の旧華族によれば、「林氏は、自らの遠縁にあたる木戸孝允を強く意識している」という。木戸は長州藩内でも穏健派に属し、「逃げの小五郎」と称されたように、過激な政治闘争から一歩距離を置いていた。薩長同盟の実現も、木戸の存在なくしてはあり得なかった。徒党を組まず、過激な言動を慎む林氏の姿勢には、まさに木戸の系譜が感じられる。
衆議院選挙に続いて参議院選挙でも敗北を喫した石破政権に対して、それでも一定の国民が支持を寄せているのは、こうした穏健でリベラルな政治リーダーにこそ、未来を託したいと願う有権者が確実に存在することの証左ではないだろうか。
日本政治の本質的な問題は、このような穏健かつリベラルな政治家層が次第に薄くなっていることにある。東京に根付く官僚主義とも、関西に見られるビジネス重視の実利主義とも異なる価値観を持つ政治リーダーを長く育んできたのは、むしろ地方であった。
そうした地方の衰退は、単なる経済的・人口的な問題にとどまらず、日本の政治における多様性と均衡を支える機能そのものの喪失を意味している。政治の機能不全の背景には、地方の教育・文化的基盤の弱体化という、見過ごされがちな構造的要因があるのではないだろうか。